落語家さんに必須のアイテムといえば、扇子に手ぬぐいです。
今回は扇子について調べてみました。
落語家さんは、扇子でいろいろなものを表現しますよね。
代表的なのは「キセル」っていう、たばこを吸うときに使います。小さい頃にみたときは、いったい何をしているんだろうと思いましたが、小学生の頃にみた時代劇でキセルでたばこを吸うシーンをみて理解しました。
様々な場面で使われる扇子について興味があればお読みください。
落語家さんが使う扇子は特別なものなの?
以前より、扇子を使う大人が増えてきました。小さなものや女性向けのきれいなデザインのものなどたくさんありますが、落語家さんが使う扇子は一般の方が使う扇子と何か違いがあるのでしょうか。
落語家さんが使う扇子は「高座扇子」!
落語家さんが使う扇子は、高座扇子と呼ぶらしく、一般の扇子よりも大きいサイズのものになります。
「大きさは7.5寸」です。
と言ってもわかりずらいですよね。
約22cmで普通の扇子よりもちょっとだけ大きなサイズです。
女性用が6寸(約18cm)か6.5寸(約19.5cm)で、男性用が7寸(約21cm)になります。
一般的な扇子と違い色や柄はありません。
落語の話の中で使われる小道具的な存在ですので、色や柄は付いていません。
落語での扇子の使い方
落語家さんが高座で扇子を使うときは、食べる仕草・煙草を吸う仕草・戸を叩くときの効果音などで活躍します。
おそばを食べるシーンなど上手な落語家さんになると、ほんとうにおそばを食べているように見えるから不思議です。
ただ、キセルにみたてて煙草を吸うシーンは、なんとなく雰囲気は伝わってきますが、実際にキセルで煙草を吸っている人を見たことがないので実感がわいてきません。
時代劇をみると、「あ~こういう風にたばこを吸うのか」ということがわかります。
戸を叩くときは、トントンと片手で戸を叩くようにして片手で扇子を床に叩いて音を出します。
そして、もう一つ大事な役目があるんです。
扇子は高座と客席を区切る?
落語家さんが高座に上がって、座布団に座ってから客席に向かってお辞儀をします。
このとき、扇子を座布団の前においてからお辞儀をします。
高座と客席を区切ります。
お客様側の世界と芸の世界を区切るんです。
落語界のしきたりなんだそうです。
芸の世界と区切ることでプロとして話芸をみせお金をいただくと言うことなんでしょうか。
高座に上がって、客席に向かってお辞儀をすると、こちらも「いよいよ始まるぞ、今日はどんな話なんだろう」と気分が高ぶります。
扇子は大事な小道具でもあり、区切りをつける大事な道具でもあるんですね。
落語家さんは扇子を何本持っているのか
扇子を小道具として使っていますが、いったい何本ぐらいストックしておくものなのか。
疑問に思ったので調べてみたんですが、これが分からないんです。
日常で使う扇子なら数本お持ちなんでしょうが、小道具の扇子はどうなのか。
以前、落語家さんがテレビ出演される前の楽屋を撮影した映像をみたことがありますが、着物や手拭はあったのですが、扇子はみえませんでした。
ある意味消耗品なのでしょうか。ここからは推測ですが、お弟子さんが用意した扇子をもって高座にあがり、演目が終わったらお弟子さんが片付ける。
これと言ったこだわりがなければそれもでいいような気もします。
また分かったら追記します。

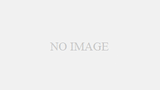
コメント
7尺もありません。もっと勉強なさっては如何でしょうか。
コメント頂きありがとうございます。
ご指摘感謝します。今一度調べてみます。