六代目三遊亭圓楽師匠が落語芸術協会に加入するというニュースをみました。
これでやっと寄席で圓楽師匠の落語が観られます。
いろいろとありますが、落語家さんは寄席で芸を磨くのが、一番じゃないかと思います。
その上で、ホール落語やテレビラジオへという風にステップアップしていくのがいいと思います。
落語家なのに寄席に出られないのはなぜ
このニュースを聞いて、なにがそんなに話題なのかと思う方に説明します。
寄席とは、新宿にある末廣亭、上野の鈴本演芸場、池袋の池袋演芸場、浅草の浅草演芸場の4箇所を言います。
ここの4箇所に出演するには条件があります。
それは、落語協会もしくは落語芸術協会に所属している落語家さんになります。
そのため、今回ニュースになった圓楽師匠は、どちらの協会にも所属しておらず、円楽一門会に所属している落語家なんです。
ほかにも、立川流といって立川志の輔師匠、立川志らく師匠も寄席に出ることが出来ません。
この4箇所のうち上野の鈴本演芸場は落語協会の落語家だけが出演できます。
寄席に出ることが凄いことなのか
それぞれに考えがあるので一概に言えませんが、芸を磨くならどこでもいいんですよ。
最近では本屋さんやカフェで落語を見ることができるので、観るほうとしては場所はどこでもいいんです。
でも、芸道として落語家を目指すなら寄席という場所は必要だと思います。
見習いから前座、二つ目、そして真打、最後はご臨終。
一つ一つステップアップするシステムになっています。
それぞれに役割があって、そこで学ぶことがたくさんあります。
だから寄席に出ることで役割を覚えることと、高座の回数を増やしながら確実に一人前の落語家になるんです。
落語の世界もサラリーマンの出世と一緒
サラリーマンにたとえるなら、見習いは新入社員、前座は入社2年目から5年目くらい、二つ目は6年目から14,5年、真打は15年以上。
新入社員は、覚えることがたくさんあり、それだけで精一杯な状態。まさに見習いです。
入社2年目から5年目くらいが、だんだんと会社のこと仕事のこと、取引先との関係など周りが見えてくるから、いろいろと気遣いも出来るようになる。
入社6年目から14,5年目は独り立ちして仕事をこなし、時には後輩の面倒をみたり上司との調整やあれこれとこなせるようになります。会社にとって貴重な人材です。落語の世界なら未来の落語会を担う人材が成長する期間ではないでしょか。
入社15年以上ともなれば、もう会社のことはわかりきっている状態と一緒。高座にあがった落語家が、パッと客席を見ただけで、今日のお客さんの状態を見極めて、話を始めるという状態です。
真打は部長で二つ目は課長か係長?
真打となればサラリーマンの世界では部長クラスといえるかも知れません。お弟子さんを持つことが出来るので、自分の組織を自分で作るような構図です。
二つ目さんが係長くらいですかね。長くなると課長に匹敵する経験値が備わって師匠のことは何でも知り尽くしている立場です。
サラリーマンなんら新入社員と部長や課長との間を取り持つ存在ともいえます。
いろいろな立場でいろいろな経験をつむことで落語に面白みが増すのではないでしょうか。
寄席は経験を積む場所
寄席は経験を積むには絶好の場所です。まさに修行の場です。
前座は、自分が出演しなくても寄席に通って仕事をしています。
本日出演する師匠のお世話や、出囃子の太鼓を叩いたり、高座を降りた師匠の帰り支度をしたりします。
もちろん自分も高座に上がりますが、それ以外にたくさんの仕事をします。
これって、師匠の落語を毎日聞くことが出来るし、お客の反応を見ることもできます。
給料がもらえなくても毎日勉強できる場所なんです。
この経験を積みながら二つ目や真打へ昇進していくんです。
前座さんにとっては絶好の場所だと思います。
圓楽師匠が寄席に出るということは、今まで経験してきたことを、寄席で演じてくれるので、前座さんはいい勉強になると思います。
まとめ
落語家さんは寄席に出られるようにして欲しいと思います。
寄席でいろいろな落語を見せてくれることは、見る側だけじゃなく、修行している前座さんにもいい勉強になるし、将来の落語界にとって重要なことだと思います。
大人の事情もあると思いますが、ぜひ前座や二つ目がたくさん勉強できるような環境を作って欲しいと思います。

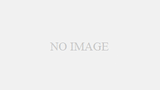
コメント