落語には滑稽噺・芝居噺・怪談噺などがありますが、今回紹介する「文七元結」は人情噺になります。
三遊亭圓朝さんが創作した長編になります。
長編の上に登場人物が7名以上となり、真打の落語家さんでも演じられる方が限られているほどの噺です。
落語の人情噺というと、お人好しすぎるほどの登場人物が出てきますが、この話は面白みも兼ね備えた演目です。
目次
あらすじ
腕のいい左官職人の長兵衛が、仕事もせずに博打に明け暮れ借金をしても懲りずに博打にのめりこんでいた年末の出来事を描いた話です。
家庭を顧みず博打に負けて帰ってくれば、女房に手を挙げて家財道具は質屋に入れてまでお金を作って博打を打つとんでもない亭主。
現代でもこんな男性が居そうですが、これは落語の世界の噺ですからこれ以上ひどい暴力沙汰が起こることはありません。
親孝行な娘の信じられない行動力
暮れも押し迫った時期に、いつものように博打を打って大負けして身ぐるみ剝がされれ家に帰ってみると、女房のお兼ねがないている。
なぜ泣いているのか聞いてみると娘のお久がいなくなったという。父親の長兵衛は「お久も十七になったんだ。いい男ができてうんぬん」と。
後添いの女房のお兼は、気立てのいいお久が博打うちの父親に嫌気がさして身投げでもするんじゃないかと心配でたまらい。
そのうち夫婦で言い合いになり、いつものように喧嘩が始まったところへ、吉原の女郎屋佐野槌(さのづち)から使いの者がやってきた。
使いの者の話を聞いて驚いた!なんと昨夜からお久を預かっているという。
女将さんが呼んでいるから来てくれと言われるが、博打でお金はないし着るものもないという始末。
女房の来ている着物をひっぺ返し、それを着て吉原の佐野槌へ。
粋なおかみさん登場!これが江戸っ子だ!
女将さんから事情を聞いて驚いたのは長兵衛。
お久は博打で方々で借金を作ったお金を返済して、父親が博打から足を洗ってまじめに働き両親が喧嘩せずに暮らしてほしいということだった。
女将は長兵衛を?りつけるだけじゃなくある約束を取り付けた。
博打でこさえた借金の五十両を渡すから、約束の期日までに働いて返済すれば、お久は返すという。
期間はちょうど一年間という約束。
それまでは預かって、習い事を仕込んでおくと。ただし約束を守れなかったら、「私は鬼になるよ」と。
お久はお店に出すという。お店に出せば刃傷沙汰や悪い病気をもらい受けることもある。
そのことを承知して、必死に働いて請け出しにおいでと。
ちなみに江戸の庶民の平均年収は二十両から三十両と言われていたので、長兵衛さんは平均年収の1.65倍から2.5倍くらい稼いでやっと五十両ですが、生活費のことを考えると平均年収の3倍くらいは稼がないと五十両は返済できないレベル。
いくら腕のいい左官職人でも平均年収の3倍を稼ぐのは困難な金額を、ぽんっと貸し付ける気質が江戸っ子!
人情噺に出てくる女将さんは気風がいい。今の時代もこういった人がいたらと思える一幕です。
まさか!五十両をくれちゃった?長兵衛どうするの?
佐野槌の女将と約束して五十両を懐に入れて、長屋に戻る途中、吾妻橋に差し掛かったところで、若い男が今にも橋から身を投げ出しそうなところを目撃!
人のいい長兵衛さんは、若い男を事情を聴いてみた。
若い男の素性を聞いてみたところ、日本橋横山町三丁目のべっこう問屋近江屋卯兵衛の手代の文七だという。
なぜ、橋から身を投げ出しそうになったのかを現代に置き換えていうと、売掛金を現金で回収したけど、スリにあってしまい帰るに帰れない。振込があればと思ってしまいましたが落語ですし、江戸時代の設定ですからね。
スリにあったというが、いくらすられたのかを聞いて驚いた。なんと五十両だという。
長兵衛さんは、働いて返せばいいじゃないかと諭すが、どうにもこうにもならない。
もし、ここで若い男が身投げすれば寝覚めが悪い。でも、この五十両はお久が見受けして作った五十両。
迷った挙句、五十両が返済できなくてもお久は死なない。でも、この男は身投げしてしまうなら、持っていきやがれとばかりに、自分が五十両を持っている経緯を若い男・文七に説明してその場を立ち去って行ったのである。
男気見せた長兵衛さんですがね、娘のお久はどうなるのさ?いくら落語だとは言え、自分の娘はどうやって女郎屋さんから請け出すの?
健気なお久さんが心配になってきた。
舞台は変わって、べっこう問屋さん。
五十両はスラれていなかった!その理由は?
お店では、文七が帰ってこないので旦那と番頭さんが心配になって待っていた。
そこへ、いわくつきの五十両を持った文七が戻ってきた。「ただいま戻りました。」
旦那様、五十両でございます。と、差し出したから旦那も番頭さんも驚いて文七に聞いてみた。
「その五十両はどうしたんだい」と問い詰めると、吾妻橋での一件を告白。
文七は、五十両を回収したお屋敷で、大好きな碁の相手をしているうちにすっかりのめり込んでしまい、五十両を置いてきてしまった。気が付いたお屋敷の人がすでに届けていたんです。
スリになんてあっていなかったんです。
吾妻橋の一件を聞いた旦那は、商売人だってそのようなことはできないと、たいそう感心したそうです。
文七から経緯を聞き出した旦那は、番頭さんと相談して佐野槌からお久を見受けし、長兵衛の住む長屋へお礼に出かけた。
お兼が長兵衛を問い詰める壮絶な夫婦喧嘩
文七を連れて達磨横町の長兵衛宅を訪ねると、昨日からずっ---と夫婦げんかのしっ放し。
なんと一晩中夫婦喧嘩。喧嘩の途中でいったん休止しようと長兵衛さんが提案するほど。
長屋の人もいつものことと気にしない。江戸時代ってこんな感じだったんだろうか。
そんな喧嘩の最中に、旦那と文七が長兵衛を訪ねてくる。
昨夜の出来事を説明して礼を言い、五十両を返した。
ところが江戸っ子。そう簡単に受け取らない、いったん出したものはいらないという始末。
なんだかんだとやり取りしてやっと五十両が収まるところに収まる。
そこへ駕籠(かご)に乗せられたお久が帰ってくる。
夢かと喜ぶ親子三人は抱き合って大喜び。わかっていても涙が出てくるほど感動します。
さて、近江屋は、文七は身寄り頼りのない身だから、ぜひ親方のような方に親代わりになっていただきたい。
これから文七とお久をめあわせ、二人して麹町(こうじまち)貝坂に元結屋の店を開いたという、「文七元結」由来の一席。
めでたしめでたしな噺です。

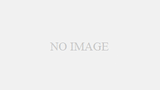
コメント