粗忽の釘は、滑稽噺の一つです。間抜けな亭主が引っ越し先で巻き起こす噺です。
現代ではワンルームのアパートの壁が薄くても、どんな人物が住んでいるかわかりませんが、落語では隣近所の事は筒抜けの世界です。
あらすじ

引っ越し当日、家財道具一式を担いで亭主だけが新居へ向かう。
ところが後から向かった女房のほうが先に到着して、荷物の整理をし夕方ごろにやっと亭主が到着する始末。
どうして先に出発した亭主が後に到着するのか、イライラした女房が訪ねると、途中ですったもんだがあって、自分が引っ越しをしていることを、すっかり忘れてしまったという粗忽さ。
あまりに粗忽な亭主に呆れた女房。怒るきもなくなった女房は、残りの荷物は明日片付けるから、せめて箒(ほうき)を掛けるために釘を打って欲しいと頼む。
この粗忽な亭主の職業が大工。職業柄、釘を打つなんて朝飯前。ところが、あれこれと女房に指図されて腹が立ち、とんでもなく長い釘を打ち付けた。
さらに釘を打ち付けたところは柱じゃなくて壁。
そもそも長屋の壁はとても薄くできている。
隣の物音が聞こえるのは当たり前。多少の物音は気にしない。
でも、釘を打ち付けてしまってとあってはさすがにまずい。
それを見た女房は、きっと釘は隣の家の壁に突き出している。
なにか家財道具などに傷を付けていやしないかと気が気でない。
そこで、亭主に隣の家に様子を見てくるように言いつける。
ちゃんと丁寧にお詫びをするようにきつく釘を指して、亭主を行かせた。
「なんでぃちくしょうめ」と文句を言いながら、行った先は隣家ではなく向かいの家。
とりあえず、引っ越してきたことと、壁に釘を打ち付けたことを説明したが、そこの住人から「いくら何でも通りの向かいの家から打ち付けた釘がこっちに来るわけがない」と言われて、この亭主やっと気が付いた。
慌てて女房のところに戻り、事の顛末を伝えると、もう一度隣家へ謝りに行くように言われる。
とにかくそそっかしくてすぐに忘れてしまうので、落ち着いて話をするように諭される。
隣家に着くなり、まずは女房から言われた一言「落ち着いていれば一人前なんだから」を思い出し、なんとか落ち着こうと、煙草を取り出す。
隣家の主人は、いったいこの人がどこの誰からもわからないまま、煙草盆をだしたり、座布団を進めてとりあえず話を聞いてみる。
しかし、肝心の釘の事が出てこない。
隣家の夫婦のなれそめや自分たちのなれそめなどを延々と話していたら、しびれを切らした隣家のご主人が「いったいなんの御用で?」と聞いてみた。
すると、そこでやっと思い出して釘の話を始める。
隣家のご主人は、どこいらへんに釘を打ったのかと尋ね、なんと釘を見つけた。なんと釘が刺さっていた場所は、仏壇の阿弥陀様の頭の上。
「阿弥陀様の上?ほーーお宅はここに箒を掛けるんですか?」
滑稽噺
この「粗忽の釘」は真打以外にも二つ目の落語家さんも高座にかけるほど、わかりやすく、随所に笑いがちりばめられている噺になります。
江戸時代の原作とされる噺がありますが、明治や大正時代には、冒頭部分で亭主が引っ越しの荷物を担いでいるときに自転車にぶつかって、ひと悶着があったります。
高座の時間によってマクラと言われる導入部分により、多少噺が変わります。
またサゲも、今回紹介した話よりさらに続きがあって、「酒を飲むと我を忘れます」というのもあります。
この噺は、新宿末廣亭で「古今亭菊志ん」師匠が高座にかけてました。
やはり寄席できく落語は、その場の雰囲気に合わせるので、サゲが変わったり噺の内容もアレンジしてあったりして、いろいろと工夫されています。
YouTubeやDVDで観たり聴いたりするのもいいですが、ぜひ寄席に足を運んでみて下さい。お勧めは新宿末廣亭です。
と、言いながら今はコロナ禍で寄席も入場制限をしてます。
寄席に足を運びにくい状況です。オンライン配信で講演している落語家さんもいます。
ぜひ、そちらでも落語をお楽しみください。
2021年5月28日まで、Youtubeにて鈴本演芸場チャンネル、浅草演芸ホールチャンネルにて、無料で落語を視聴できます。
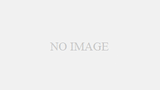
コメント