前座を何年か務めて、師匠から認められ協会の承諾を得ると「二つ目」に昇進。
名前の由来は、「前座の次に高座に上がる」、いわゆる二番目に高座に上がることをさして二つ目と呼んでいます。
前座時代は、寄席の裏方としてあくせく働きながら、師匠に稽古を付けてもらい、最低でも2,30個の噺を覚えます。
二つ目と前座の違い
二つ目に昇進すると、前座時代と違い、毎日寄席に行かなくてもいいし、寄席へ行くときは、自分の出番があるときだけになります。
とはいえ、師匠によっては前座時代と同じように寄席に通って、落語漬けの生活をするように指導する師匠もいるようです。
真打になった時よりも二つ目に昇進した時のほうが嬉しかったという落語家さんもいます。
前座時代は、とにかく寄席での仕事がありながら、サラリーマンのように給料が保証されている訳ではなく、ひたすら修行の日々となります。
二つ目になると高座にあがると、割といって入場者数に応じて出演料がもらえます。ほんの数千円ですが。
だからこれだけでは生活ができません。そのため、師匠の落語会に一緒に出してもらったりしながら食いつないでいくんです。
前座と違い、落語家として認められますが、だれもが安定した生活ができるわけではありません。
落語家と認められてもまだまだ修行が続きます。
二つ目の期間はどのくらいなのか
二つ目から真打になるには5年から10年くらいかかります。
真打になるまでに、新しい噺を覚えたり、違う師匠のところで稽古を付けてもらったりしながら毎日が修行です。
落語以外にも歌舞伎や演劇を鑑賞したりする二つ目さんもいます。
寄席以外のところでも、どんどん落語を演じて腕を磨きます。
少しづつ認知されてくるとテレビやラジオの仕事も増えてきます。
こういった仕事をしながら寄席に出て落語を演じます。
とにかく落語の事を考えて、ひらすら芸を磨きあげていく期間なんです。
最近はイケメンと言われている二つ目さんが多く、若い女性にも人気があります。
がんばれ!二つ目さん!

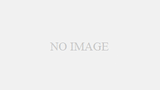
コメント