古典落語に「尻餅」という噺があります。
年末の貧乏な一家のお噺です。落語の世界だから許される愉快な内容です。
目次
「尻餅」あらすじ
年の瀬に長屋に住んでいる一家は、正月を迎えるために、餅を搗くことができないほどの貧乏。
隣近所からはぺったんぺったんと餅を搗く音が聞こえてくる。
この状況にたまり兼ねたおかみさんは、亭主に音だけでもいいから餅を搗いている様にして欲しいと頼むんです。
この言い回しが、落語の世界のおかみさんの度量ですね。
ストレートに言わない。本当はお金を工面して来いと言いたいところ。
ところが、亭主の八五郎が間抜けと来てます。
「よし!任せておけ!その代わり絶対の怒るなよ!何が起きても起こるなよ!」と。
夜、子供が寝たのを確認すると、亭主は一旦長屋から出ていく。
そしてここから芝居が始まる。
周り近所に聞こえるように、餅屋を装って自分の家にやって来る。
「餅屋でございます。八五郎さんのお宅はこちらですな。」
こんなことしても声でわかっちゃうのにと、思いながら噺は進みます。
すべて”音”だけで独り芝居で進めていきます。
ただ、お餅を搗く音だけは八五郎だけではできません。
餅屋さん(八五郎):「では、餅を搗きますので・・・
八五郎:「おっかあ、臼を出してくれ」
おかみさん:「臼なんてないよ」
八五郎:「いいから尻を出せ」
おかみさん:「えっ?お尻?なんで?」
八五郎:「尻を叩いて餅を搗く音にするんだよ、いいから着物をめくって尻を出せ!」
ここで八五郎は、初めて女房の尻を見て、「白いお尻だなぁ」と見とれてしまう。
当時は、バックスタイルで事をすることがタブーとされていました。
おかみさんは、仕方なしにお尻をだすと、手に水を付けてお尻を叩き始めます。
「ペッタンペッタン」だんだんと白いお尻が赤くなってきておかみさんがたえきれなくなります。
おかみさん:「餅屋さん、あと何臼搗くんですか?」
餅屋(八五郎):「あと二臼あります。」
おかみさん:「じゃ、残りはおこわにしておくれ。」
尻餅はいつごろ作られたのか
原題は中国明代の笑話本「笑府」に類話があり、これが元ではないかと言われています。
日本では明和五年(1768)に抄訳が刊行され、以後に多くの落語、小ばなしのネタ本になった本です。
この中に、似たような話があるのですが、特定はできていません。
江戸時代の太平の世で生まれた噺です。
サゲ(落ち)が関東と上方では違う
上方落語で演じられているときのサゲ(落ち)は「白蒸(しろむし)でたべとくれ」。
江戸落語では「おこわにしておくれ」という風になります。
「白蒸(しろむし)」というのは、もち米を蒸してまだ搗いていない状態です。
おかみさんからしたら、「もうこれ以上、お尻を叩かないで!」と言いたかったのでは。
大阪の食文化に、もち米を蒸して食べる習慣があったようです。
白蒸しを竹の皮に包んで梅干をいれたものがお弁当や携帯食としてお祭りで食されました。
だから、上方落語のサゲのほうがいいと思いますが、江戸では白蒸しは馴染みがなかったため「おこわ」になったのでしょう。
笑福亭と三笑亭
上方では笑福亭系の噺で、五代目・六代目松鶴の十八番。
江戸では八代目三笑亭可楽の演出が現在の基本になっています。
貧乏でも知恵を働かせて暮らしている江戸時代の情景が浮かんでくる噺ですね。
それにしても、よくこんな間抜けな八五郎に奥さんがいると感心したことと、この奥さんが八五郎の無茶ぶりに付き合うのが現在ではありえない夫婦像です。
それにしても、甲斐性のない男ほど見栄っ張りなのでしょうか。
思わず笑ってしまう噺ですが、毎年つつがなく年末を迎えたいものです。
桂歌丸師匠はニュヨーク公演で「尻餅」を話しました。
きわどいところもあるネタですが、反応は良かったそうです。

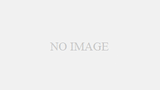
コメント