好きな演目の一つに「宮戸川」があります。
古典落語の一つとして古くからあるのですが、それほど多くの落語家さんが高座で、この噺をしていないようです。
この噺は、「お花と半七の馴れ初め」の前半部分と、夫婦になった後の後半部分にわかれます。
前半と後半を演じると30分以上の展開となるため、前半だけ口演されることがあります。でも、前半だけだと「宮戸川」は一切出てこないんです。
これだけの噺になると、寄席では時間的に口演できないため、独演会などで演じられる噺です。
また後半部分は、とても凄惨な部分もあって落語と言うよりも、芝居を見ているような感じにさえなります。
そのためなのか、宮戸川を口演する噺家さんも少ないのだと思います。
目次
柳家喬太郎
宮戸川を初めて観たのは、TBSテレビの「落語研究会」で放送されていたときでした。
内容も知らずに噺を聞いてましたが、「まくら」の部分がなければ、たぶん落ち(さげ)は分からなかったと思います。
柳家喬太郎さんは、「まくら」が非常にうまい落語家さんの一人だと思います。
そして、落語と言うより、一人芝居を見ているような感覚です。
宮戸川は、現在の隅田川の浅草周辺流域あたりをさします。花川戸から駒形くらいまででしょうか。
この宮戸川を演じる落語家さんは非常に少ないそうです。
その理由はのちほどに、噺のあらすじを紹介します。
宮戸川 前半 半七とお花の出会い
日本橋小網町の質屋のせがれ半七は、友人宅で将棋を指していて帰りが遅くなってしまい、締め出しを食った。
勘当を言い渡されて半七が謝っているところへ、隣家でも同じような騒ぎ。
友人宅でカルタをしていたら帰りが遅くなってしまった船宿・桜屋の娘お花。
こちらは日ごろから折り合いの悪い義母から、締め出しを食った。
半七は、締め出しをくらうと、いつものように霊岸島に住む叔父の家に一泊することにしている。
霊岸島は、現在東京都中央区新川(しんかわ)のこ。隅田川、日本橋川、亀島川に囲まれたあたりになります。
叔父さんのところへ向かおうとしたところお花が、「わたしも一緒」にと言い出す。連れて行くのは良いが、早合点する叔父さんが、お花さんと恋仲だと思われるの嫌なので断ったのですが、なんだかんだ着いてきて、叔父さんに勘違いされる始末。
布団がひと組しか用意されず、半七は仕方ないと思ったのか寝ようとする。お花はまんざらでもない様子。
二人で一組の布団で寝始めると、ゴロゴロ、ゴロゴロと雷鳴。これに驚いたのがお花。思わず半七に抱きついてしまう。
抱きついた拍子に、お花の白い足が見え、半七もその気になって・・・・。
翌日、覚悟を決めた半七はお花と所帯を持つことを叔父さんに告げると、「任せておけ」とばかりに話を進めていきます。
お花の両親は大喜びなんですが、半七の親父さんは頑固者。嫁入り前の娘に半端なことをするやつを家に上げるわけにはいかないの一点張り。
それならばと、叔父さんは半七を養子に貰い、横山町辺に小さな店を持たせて二人が仲むつまじく暮らしたという、お花半七なれそめ。これで前半は終了です。
それにしても、そこまでお節介な叔父さんの存在が落語の中で生きている人物らしくてとても好感のもてる人物です。
こういうのを”粋”と言うんでしょうか。
ここまでだと宮戸川という川は一切出てきません。
宮戸川 後半 凄惨な場面は聞くに堪えないかも?
半七とお花は所帯をもち、四年ほどたったある日、お花は店の小僧を伴に浅草の観音様に参った後に、突然雷がゴロゴロ~と。
勢いよく雨も降り出し、小僧はお花を雷門のところで待たせて傘を捜しに駆け出した。
あまりの雷鳴にお花は気絶してしまったんです。
それを見ていたならず者が三人が、気を失ったお花を連れ去ってしまったんです。
小僧がしばらくして戻ってくると、お花の姿が見当たらない。
血相を変えた小僧は、必死なって探しても見付からない。
店に帰って半七に、お花が行方知らずになったことを伝えると、半七を必死になってお花を探した。
諦めきれない半七でしたが、必死になって探すこと一年。
泣く泣く葬式を出すことになった。一周忌に菩提寺の参詣の帰りに、何気に船宿へ寄り半七がたまたま乗った船で事件が起こるんです。
船頭が舟を出そうとすると、もう一人客が乗ってきた。実は酔っ払った船頭だったんです。
二人の酒を酌み交わしながら舟になっていると、その船頭が一年前に雷門で気絶していた女をさらって輪姦したうえに、お花の実家で働いていた人物で、気を取り戻したお花を殺して宮戸川へ捨てたことをベラベラと自慢げに喋りだした。
半七は「これで様子がガラリと知れた」と芝居がかりになる。三人の渡りゼリフで、
「亭主というはうぬであったか」
「ハテよいところで」
「悪いところで」
「逢ったよなァ」
・・・・というところで小僧に起された。
女将さんが下でお呼びですよ。
「え?、おめぇ今日はお花の・・・・」
「今日は叔父さんの法事ですよ。」
「旦那さんうなされてましたけど、夢でも見たんじゃないですか?」
「夢・・・夢か・・」
女将さんは亭主を起すために小僧を使いに二階へやったところで
「夢は小僧の使いか・・・・」これが落ち(さげ)になります。
昔は、夢を見るのは体が疲れているからだともいわれていて、五臓六腑が疲れると夢を見るともいわれていました。
TBSの落語研究会で柳家喬太郎さんが演じていたのも見ました。
この話はほとんど笑いがありません。特に後半部分はお花がさらわれてから酷いことをされる場面も合って演じる落語家さんも少なくなってしまったようです。
ただこの話のいいところは、最後に夢で終わるところ。よかったーと安堵しました。
落語と言うより舞台でお芝居を見ているようで、背中がゾクゾクするほど痛ましい場面もありました。
笑いがなくても感銘した話です。
でも、演じ手が少なすぎて見ることができない作品です。
演じ手が少ない理由
演じ手が少ないのは、笑いの要素の少ない話のうえ、落ちも夢ときているので、段々と演じ手が少なくなったんです。
柳家喬太郎さん以外は、柳家個小満んさんくらいしかしないのではないでしょうか。
宮戸川が作られたのはいつごろ
この話が作られたのは京都で起こった心中事件を元に1712年に浄瑠璃として作られたものを、初代三遊亭円生がこれを道具入り芝居噺に脚色したのが原型とされています。
明治の中期までは、前半後半を通しで演じていたのですが芝居噺が廃れだし後半部分が演じられることも少なくなって用です。
そして今ではほとんど演じられることがなくなりました。
駒形あたりにいったらこの話を思い出してください。

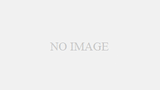
コメント