目次
二番煎じ あらすじ
火事と喧嘩は江戸の華と言われていますが、江戸時代の火事は一度起きるとひとたまりもないほど。特に冬は火事は起きる可能性が大いにあります。
そこで、自分の町内は自分たちで守ろうと商家や名士たちが集まり夜間に町内を見回ろうと自身番という組織が出来上がりました。
とは言ううものの冬の夜の冷え込みは半端ないくらい冷えます。ヒートッテックのような洋服もホカロンもあるわけもなく着物の上に袢纏を羽織って見守ります。
あまりにも冷えるので、月番の旦那の提案で夜回りを二班に分けて交代で回ろうと言うことに。
この提案には一同が賛成し、早速月番の旦那がチーム編成
まずは最初の班が夜回りに出かけ、残った班は番小屋で暖を取りながら待っているという具合。
最初の班はチームリーダーが月番の旦那で、他の人選は次の通り。
・月番の旦那(リーダー)
・提灯係の宗助さん
・拍子木係の歌のお師匠さん
・鳴子係の旦那
・金棒係の辰っあん
それでは、夜回りに出発です。
ここ数年は大都市圏ではあまり見られなくなったと思いますが、夜になると町内の方々が「火の用心!」の掛け声の後にコンコンと拍子木を打って回っていた光景ですね。
今なら、これでもかというくらいの防寒ですが当時は今以上に冷え込んでいる。
拍子木は着物の袖に仕舞い込んでコンコンとやるものですから全く響かない。
鳴子は横着をして鳴子の紐を帯につけてぶら下がった鳴子を膝で打つ。
金棒は、引きずるのでほとんど聞こえない。
寒いので誰も「火の用心!」の掛け声がない。
月番の旦那が、拍子木係の謡の旦那にお願いすると「火の用心!」とならず「ひ~の~よう~じん」と謡調になる始末。
鳴子係の旦那に頼めば都々逸調になっていまう。
こんな調子で、とりあえず番所までたどり着き次の班にバトンタッチ。
とにもかくにも冷え切った体を温めようと、火鉢に手をかざして暖を取っていると、誰かが「出掛けに娘が持たせてくれた」とお酒の入った瓢箪を出す。
すると月番の旦那が「あなたね、どうしてそういうものを持ってくるんだね。ここをどこだと思ってるんだい」と言うものの
「辰辰っあん、土瓶の中にお茶が入ってるだろ。それを捨てちゃってね。それにいれたらどうだい」
「酒を入れてどうすんだい」
「バカな事を言うね。冷で飲んだら体に毒だから燗していただくんだよ。土瓶に入れときゃお役人が来たってわかりゃしないよ。実はね私も持て来たんですよ。宗助さん、そこの戸に突っ張り棒を指しといて」
すると、もう一人が「実はあっしは酒の肴に猪の肉を持ってきたんで。」
「猪の肉!あなた気が利いてますよ。でもね、鍋がないじゃないか。」
「鍋は背中に背負ってきました。」と袢纏を脱ぐと背中に鍋がある。
これで、酒も肴もそろって皆で回し飲みをしながら獅子鍋をつつく。
こんあ調子でいつの間にやら酔いも周り都々逸を歌いながら意気揚々とやっていると、戸をたたくような音が聞こえてくる。
月番の旦那は、犬か何かだろうよ「シッシッ」と。
すると、さらに戸がドンドンと叩かれ「番はおるか!早く戸を開けと!」
なんと、このタイミングでお役人が見回りに来てしまった。
一同は慌てて土瓶を鍋を隠して戸を開ける。
するとお役人は「拙者が戸を叩いた時にシッシッと申したな」
月番の旦那は「滅相もございません。寒いので火(し)を付けいようと言ったのでございます。」と、苦しい言い訳。お役人は「先ほど土瓶を隠したな。」
仕方なく土瓶を出し「風邪気味なもので煎じ薬を飲んでおりました。」
するとお役人は「そうか、ならば拙者もその煎じ薬とやらをもらおうか」そう言って酒をグイっと飲み干す。
お役人は「この煎じ薬は本当に効くのか?もうちょと試してみよう」と、ぐいぐいと飲み始める。
そして「鍋のようなものもあったな」と。
観念して鍋も差し出すとお役人はぺろりとたいあげてしまう。
月番の旦那が「もう煎じ薬がございません。」
すると、お役人は「拙者は一回り見回ってくる。それまでに二番を煎じておけ」
二番煎じは、前半の楽しさと後半の楽しさがある噺
前半は、夜回りの5人が寒さを凌ぎながら、特徴のある「火の用心」の掛け声や道具をいい加減に扱う様を描いています。
寒さが厳しいながらも、何とか役目を果たそうとするも、拍子木はちゃんと打てない、「火の用心」の掛け声は長唄のようになったり都々逸のような調子だったり、町内を回る様がなんとも滑稽な状況です。
後半は番小屋に戻って、みんなの気持ちが同じで大人の楽しみとして「お酒」と「鍋」で体を温めたい!と。
お酒を飲むために、夜回りに行ってきたようなもので、結局はみんなお酒が大好きなんです。
そこに、お役人さんが番小屋を見回りに来るんですが、お酒と知りつつ煎じ薬と言われて、何も咎めずに飲むという、お互いに大人の対応をするんですが、立場を上手に利用して「二番を煎じておけ」という洒落がわかる粋な感じですよね。
この部分が落語のいいところなんですよ。
恵比寿ルルティモ寄席2021
今回、この「二番煎じ」は「恵比寿ルルティモ寄席2021」に出演された三遊亭兼好さんが高座にかけました。
おおよそ40分くらいの割と長めの尺でした。
このほかに「春風亭一之輔」「桃月庵白酒」「橘家文蔵」という豪華な顔ぶれでの落語会です。
三遊亭兼好さんは、笑点でおなじみの三遊亭好楽師匠のお弟子さんです。
話のリズムと描写がよくて、本当に5人の旦那衆がそこにいて夜回りしている情景が浮かんできます。
こういう話し方をされると、「落語を聞く」と言うより「落語を観る」という表現がぴったりなほどです。
お酒を飲むシーンは、本当に飲んでいるようで観ているこちらも飲みたくなるほどです。
是非ですね、寄席やホール落語などに出かけて生で観て下さい。
でも、まだまだコロナが怖いという方もいますので、ご自宅でDVDやCDでも楽しめます。
コロナ禍も過ぎ去ったことですから、ぜひ寄席やホール落語で楽しんで下さい。

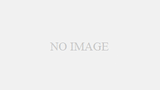
コメント