ゴールデンウィーク前の4/25日、平成時代最後の寄席に行ってみました。
場所は日本一の歓楽街から少し離れた新宿三丁目界隈にある「新宿末廣亭」です。
夕方5時を20分ほど過ぎた頃に入場しました。
いす席は7割くらいの入りでしたが、入り口から右手の座敷席には3,4人くらい座っていました。
目次
新宿末廣亭は座敷席が最高
なぜ座敷席がいいのかというと、落語家さんの目線がちょうどいい具合にあうんです。
まるで、こちらを見ながら話してくれているような感じがいいんです。
寄席は都内に4箇所ありますが、座敷席があるのは末廣亭だけではないでしょうか。
ただし、3時間もあぐらだと足が疲れるのと、混んでくると若干窮屈さはあります。
これは好みですが、いす席ならできるだけ前に座ったほうがいいです。
背が低いと、前に座高の高い方が座っちゃうと頭が邪魔でよくみられません。
それもあって座敷席で鑑賞しています。
テレビやYouTubeじゃ見る事ができない芸ばかり
テレビのバラエティ番組だとか、YouTubeなどの動画サイトでは見る事ができない芸がそこにはあるんです。
年末にあるM-1グランプリやピン芸人のR-1グランプリなども、勢いのあるタレントさんが優勝を目指して頑張っていますが、彼らが何を目指しいているかわかりませんが、そういう優勝を目指したものじゃないんです。
寄席にはメディアで見る事ができないけれど、芸暦30年や40年の長い間、舞台で生きてきた芸人さんを生で見る事ができるんです。
動画なら何度も再生できますが、いま目の前で古典落語を演じている落語は、大げさに言えば2度と見る事ができないんです。
不思議ですよ。古典落語というのは。もう何十年も昔の作られた話を、落語家さんたちが語りついで来たいるのに、演じる落語家さんによって、まるで違う話のように感じる事もあります。
それは、”いま”という同じ空間と時間を共有しているからだと思います。
ただ、面白おかしく話すのではなく、高座に上がる直前に演目を決める事があります。それは、同じ話がかぶらない様にすることと、会場の雰囲気で話を決めるんです。
テレビなどは事前に、何をするかを決めていますが、演芸場では予め決めてはいないんです。だから、何をするかは実際に行ってみないとわからない。
でも期待を裏切らないから、いつも会場はほぼ満席な状態。
結果、この日も夜7時を回った頃には、ほぼ満席。
空いていた座敷席も、いつの間にやら座るところも無く、後ろを振り返れば立ち見の方もいらっしゃる。
寄席は日常には無い空間
寄席は、特に新宿末廣亭は日常にはない空間を味わえます。入場すればすぐに分かりますが、劇場の雰囲気が昭和以前の雰囲気を味わえます。
木造作りの建築物で、座敷席にある下駄箱は木製なんです。座れば分かりますが、下駄箱であり上は飲み物などちょっとしたものが置けます。
画像撮影禁止のためお見せする事はできませんが、もしも末廣亭に行ったなら座座敷席を利用してみてください。
スケジュールはあくまでも予定なのが寄席
入場時にスケジュール表(香盤表)を貰うのですが、これはあくまでも予定であって、当日スケジュールに載っていない落語家さんや芸人さんが出演されます。
基本的に10日間同じスケジュールですが、どうしても都合が悪いとなると、変りの落語家さんや芸人さんが主演されます。
この日は、主演の順番が変わったり違う芸人さんは登場しました。何事も無いかのように、進んでいきます。もちろん会場を沸かして去っていきます。
こういうことに慣れているというのか、もう当たり前なんでしょうが、さずがプロの仕事です。
おわりに
寄席は365日毎日興業しています。ほぼお昼から夜の9時くらいまで。多くの落語家さんがいますが、メディアで有名な落語家さんは数えるほど。
何度か寄席に行きましたが、笑点に出演している落語家さんは林家木九扇師匠くらいです。他にも大勢の落語家さんがいらっしゃいます。
メディアに出なくても、すばらしい落語家さんはたくさんいます。
毎日やっている寄席に一度行ってみてください。

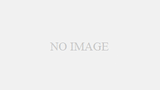
コメント