「落語にも付加価値が必要だ!」と、あの立川談志さんが言われたそうです。
付加価値を生み出すのが工夫であり、その工夫が新たなものを生み出す。
いっけん無駄だと思えることでも徹底して行動してみることから、何かが生まれるのではないでしょうか。
そこで、落語に付加価値ってなんだろうと考えてみました。
古典落語こそ付加価値の集大成?
古典落語は明治時代以前に作られた落語ですが、今日まで古典落語が継承されてきたのは、この工夫があってこそではないかと思います。
噺の大筋内容は同じであっても、時代に合わせてちょっとだけ登場人物を変えてみたり増やしてみたり工夫を凝らして発展させてきたからこそ古典落語として今日まで続いているのだと思います。
工夫に工夫を重ねた作品が新作落語だと思います。
2017年4月に渋谷で行われた春風亭昇太さん、林家彦いちさん、三遊亭白鳥さんの3人による新作落語を鑑賞して来ました。
新作落語
初めて新作落語を体験しましたが、とにかく笑える作品でした。
紹介した3人は古典落語だけじゃなく新作落語にも力を入れて活動しています。
春風亭昇太さんと三遊亭白鳥さんは、新作落語のユニットを組んで活動していたほど、新作落語に精力的に取り組んでいます。
当時のユニット名は「SWA(すわっ)」と名前で活動をし2011年には解散してしまいました。
|
|
林家彦一さんはSF的なタイムマシーンで過去の自分に合うという設定の噺でした。
落語でSFチックな噺は想像できないかもしれませんが、斬新というより落語に対する固定概念を打ち破ってくれました。
ちょっと新作落語に抵抗があったんですが、新作落語は演じ手の工夫がふんだんに盛り込まれています。
新作落語の創意工夫 サラリーマンの仕事と同じ
新作落語は何度も作り直したり、演じるその日にちょっと話を作り替えたり、客席の反応を観ながら内容を作り替えていくと思います。
これってサラリーマンの世界も同じで、特に営業さんならわかるのではないでしょうか。
営業トークを確立するまで何度も何度も試行錯誤したり、プレゼンのために資料を何度も書き換えたりしながら作り替えることと一緒です。
また、お客様と話をするときは、いきなり商品説明なんてしないですよね。
まずは、お客の興味がありそうなことや世間話的なことを話しながら、自社の商品説明へと移っていきます。
落語も、高座に上がったとたん落語をはじめません。
まずは、お客を観ながら時事ネタや話題のネタで様子を見ながら前ふりをして本題にはいります。
最後は落ち(さげ)につなげていきます。
営業に例えるなら、最後の落ちはクローズとなり注文をいただけるところ。
いかにリサーチして顧客(観客)の心を掴み、商品(本題)の必要性を説いてクローズ(落ち)へと持っていく。
サラリーマンのあたたこそ、落語家さん公演に出かけて落語を聞くことは、上司の話を聞くより100倍以上価値があります。
落語の公演へ行けない方へ
落語の公演へ行けない方は、まずはYOUTUBEなどで落語を聞いてみて下さい。
短い話でもいいので、いくつも見て下さい。
そのうち気になる落語家さんが見つかります。
なんども聞くうちに、落語の素晴らしさが理解できると思います。
まずは、落語を聞いてみましょう。
そして、仕事に役立てて下さい。

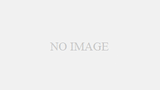
コメント