2019年の落語はじめは新宿末廣亭
世間は正月気分がすっかりと抜け、いつもと変らない日常ですが、寄席は1月20日までがお正月らしいんです。
落語好きな友人に誘われて、午後3時ごろに新宿末廣亭に到着。
チケットを購入し入場すると、いす席はほぼ満席。
係りの女性から、左右にある座敷席を進められ右側の座敷席へ。
靴を脱ぎ、座席のところにある下駄箱?に靴を入れて座りました。
座って初めて気が付いたんですが、ちょうど高座と同じくらいの高さなので、落語家さんの顔がよく見えます。
ただ、胡坐をかいていたので、結構足がつらいです。
構成は2部になっています。お昼の部と夜の部で、お昼の部は1:00から4:30まで、夜の部は5:30から9:00まで。
昼夜の部で入替なしで、最後まで見ることができます。入場するときにチケットとプログラムをもらいます。
本日の演者が出演順に書かれています。このプログラムに名前が載っていないのですが高座に上がる方がいます。
それは前座さんです。プログラムに書かれていないので、お昼の部の開始15分前くらいに出てきて、習ってきたであろう落語を披露します。
もし、全部見たいと言う方は、開始20分前くらいに到着していると前座さん含めて全部見れます。
目次
構成はどうなっているか
演目の構成は、落語以外に漫才・神楽・奇術・漫談など、いろいろな芸を見ることができます。
メインは落語ですが、合間に 漫才・神楽・奇術・漫談など があります。
開始から2時間程度で中入り(休憩)が10分程度あります。その後は最後まで休憩なしで落語を楽しめます。
演芸場での楽しみ
演芸場の楽しみは、なんといってもテレビでは見ることができない芸人さんばかりはみえれることです。演芸場を主としている芸人さんです。
持ち時間が一組15分程度、主任(トリ:最後に出てくる方)はおおよそ30分くらい。限られた時間内に、客席の状況に合わせて笑いを取るんです。
また、落語は高座に上がる前まで、どんな演目をするか落語家本人も分からないんです。
なぜかと言うと、自分より先に高座に上がった落語家さんの演目を確認して、それ以外の演目を行います。
ネタが誰ともかぶらないようにするためなんです。
さらに、高座に上がって、客席の様子を見て、急遽演目を変えることもあるそうです。
今回の演目は?昼の部
午後3時から入場したので、昼の部の途中でしたが、中入り前で柳家小さんと鈴々舎馬風さんを見ることができました。
馬風さんは、世相を切る小話でしたが、年齢の割に世間の出来事をよく勉強されていると感心しました。
ここで中入りとなりしばし休憩。
休憩明け一発目は歌る多一門による「松づくし」。一門と言っても歌る多さんとみるくさんの二人で、いろいろな「松」を魅せてくれました。これは実際に見ないとわからない芸です。
そのあとは、代演で春風亭勢朝さんが出演されました。落語と言うよりも、新選組の話からいろいろ脱線して、新選組の話しはこの次にと言って退場。
続いて、林家正蔵さん。こちらは新作落語でした。割と面白かったですね。
そのあとの桂文楽さんは40年くらい前にペヤングソースやきそばのCMに出ていた方でした。次に、林家木久扇さんは、師匠の事や笑点の話で笑いが絶えない舞台でした。
橘家橘之助さんでしたが代演はのだゆきさんでした。初めて見ましたが楽器を使った漫談?と言うのか、とにかくちょっと変った芸風でした。
主任(トリ)は柳亭市馬さん。落語協会の会長さんです。夫婦愛を描いた「厩火事」でした。この話は、夫婦がどれだけ相手を思っているかを試した噺とされています。
と言うのも、最後のオチをどう解釈するかでお互いがどう思っているか変ってくるんです。あなたはどちらでしょうか。
ここで昼の部が終了となります。帰る方が半分、そのまま居座る方が半分くらいいました。
今回の演目は?夜の部
では、夜の部ですが、最初は柳家小はぜさん。演目は「饅頭こわい」でした。演芸場で初めて聞きました。有名な古典落語ですが新鮮に感じました。
続いては、漫才で笑組のお二人です。コンビ結成33年の超ベテラン。何度見ても面白いですね。M1グランプリとかに出ているような漫才とは全く違う、演芸場じゃなければ見ることができないコンビです。
今回はお正月という事もあり、漫才の最後に「南京玉すだれ」を息の合った調子でやってました。舞台に立つ芸人さんは、本当にいろいろと芸を身につけています。
次は柳家〆治さんで「初天神」でした。いかにもお正月にピッタリな演目でした。
続いて正朝さんが古典落語の「初音の鼓」、林家しん平さんが花園神社の狛犬の噺と続きました。
ここで、中入り後に登場するはずの柳家さん喬さんが出てきてびっくり。優しい語り口で、味わい深い話し方をされるのでとても好きな落語家さんの一人。
その後に高座に上がったのが一番弟子の柳家喬太郎さん。古典も新作もどちらもでき、2019年3月には自身の新作落語が舞台化されます。
今回は新作落語でした。喬太郎さん独特の世界観が何とも言えません。古典落語もでき、新作落語は、唐突なものからラブコメディありの一人芝居的なエンターテイメント満載な落語です。
初音家左橋さんが「粗忽の釘(そこつのくぎ)」そそっかしい町人の噺です。古典落語にはよく出てくるタイプの町人です。こんなにもそそっかしくておっちょこちょいでも生きていける逞しさが羨ましいです。
続いては、漫才の「すず風 にゃん子金魚」さん。女性の漫才ですが、とにかく動きが凄い!舞台をいっぱい使って動き回る。二人が客席とやり取りする面白さと、年齢を感じさせないしなやかな動きはいつもても笑えます。
そして次は柳家権太楼さん。出てくるなり「待ってましたー」の一声に「ありがたい事です。とはいえ、本当に待ったあ?」客席も大笑い。また、最前列のお客さんが声を掛けると、見事に切り返し笑いに変える。今回は小話だけでしたが、十分に楽しめた高座でした。
そのあとは、柳家小満んさん。縁というまくらから、古典落語の「宮戸川」。まさか演芸場でこの噺を聴けるとは思いませんでした。実際にこの噺をすると30分以上掛かります。今回は短く途中で終わりましたが、じっくりと聞きたい噺です。
ここで、夜の部の中入りに入ります。一斉にトイレに行列ができます。男性は簡単に済ませられますが、女性は大変だなーーと思います。
中入り後は大神楽から始まりました。獅子舞と太鼓に笛とお正月らしい出し物です。
次は桂南喬さん。古典落語の「ふぐ鍋」。ふぐの毒に恐る恐る手をつけるところに・・・。誰か他の人に食べさせて安全を確認してから食べようとしたが、結局食べさせようとした人は食べずに、自分たちが最初に食べてしまう。食べたと思っていが実は食べずに様子を見ていた始末。
続いて春風亭一朝さん。古典落語の「湯屋番」。古典落語に欠かせない、道楽者の若旦那が主人公の噺。吉原通いに夢中になりすぎて感動された挙句、銭湯で働く事になったが、これがまた適当な事をして・・。
さて、そろそろ主任(とり)が出てくる時間が迫ってきました。その前に、林家正楽さん。この方は落語ではなく「紙きり芸」なんです。
A4のコピー用紙くらいの大きさの紙を挟み1本だけ使って表現します。最初は羽子板を打つ女の子。ほんの1,2分で出来上がり。出来映えに拍手喝采!
ここから、客席にリクエストを募ります。このときを待っていたかとばかりに男性数名が手を上げてリクエスト。この時期らいいリクエストもありましたが、最前列の男性のリクエストに客席は大笑い。お題は「キリンの親子」!
これには正楽さんも若干苦笑い。ただ、「私が一番得意なのがキリンの親子」と切り返し、またまた大笑い。出来上がったキリンの親子に、リクエストした男性は大喜び。どんなリクエストにも答えてくれるけど、なぜキリンの親子なのか今でも不思議(笑)
さて、いよいよ主任(とり)の登場です!今回の主任(とり)は柳家小三治さん。なんと人間国宝なんですよ。もう、小三治さん、いや小三治師匠見たさにやってきた方も多かったはず。
ところが、高座に上がってきたのは春風亭一之輔さん。本人も、「そういうものだから。だって人間国宝ですよ。だからたまーーに高座に上がればいいんです」と。実力のある若手の落語家さんの登場ですし、こういったことは寄席ではよくある事。ただ、小三治師匠を見たかった。
今回は古典落語の「味噌蔵」。ケチな男の噺。
どのくらいケチなのかと言うと、結婚するとお金がかかる、子供が生まれるとお金が掛かるという始末で、いまだに独身。
親戚一同から、結婚しないなら縁も切るし商売の取引もしないと脅されて、しぶしぶ結婚。
ところが、子供を授かると大変だと、寝室は別々。
ケチ故に、布団は薄く、真冬は凍えるほど。この寒さに耐えかねず、女房の布団に潜り込んでしまったのが運の尽き。
あっと言うまに女房のおなかは大きくなってしまい、十月十日が近くなり番頭さんから、「おかみさんを実家に預けてしまえば、お金はすべてあっち持ちなるはず」
と言う事で、女房を実家に預けて・・・・
おおよそ30分ほどの高座を勤めました。
今回は小三治師匠に会えませんでしたが、一之輔さんの落語が聞けたのでよかったです。
まあ、人間国宝に3,500円払ってみようと言うのがよくないですね(笑)
新宿末廣亭 注意事項
初めて興しになる方へ、いくつか注意事項をまとめておきましたので参考にして下さい。
昨今、SNSで画像をアップされる方がいますが、末廣亭は撮影が一切禁止されています。
アルコールもNGです。
一度退場すると再入場はできません。
途中から入場したときは、係員さんの指示に従いましょう。
飲食はできますが、周りの方への配慮を忘れないで下さい。
演目中はトイレに立たないようにしましょう。演目の合間に行きましょう。
個人的に感じた事ですが、お互い楽しく鑑賞できる様にしましょう。

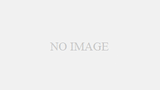
コメント