出囃子ってご存知ですか?
落語家さんが舞台の袖から登場するときにかかる曲を出囃子といいます。
落語家さんごとにテーマ曲があるんです。
三味線と太鼓と笛という構成で演奏されます。
寄席などでは、出囃子を聞いただけで、どの落語家さんが登場するかわかるそうです。
出囃子は落語家さんほとんど一人ひとり違う曲です。
そんな出囃子について調べてみました。これも落語の楽しみの一つです。
目次
出囃子はいつから始まったのか?
もともと上方のほうで始まったのがきっかけとなり、大正時代に東京でも取り入れられ始めました。演奏に使われるのは、三味線・太鼓・笛などになります。
もともと江戸落語は、太鼓だけの「片シャギリ」と呼ばれる演奏だけだったそうです。これをた5代目柳亭左楽を中心とする睦会が取り入れだし、今日まで続いています。
出囃子は誰が演奏している?
出囃子は誰が演奏しているのでしょうか。
三味線は下座(げざ)さんが演奏します。三味線の演奏は全て女性が受け持っています。
演奏する方を下座さんもしくはお囃子方と呼びます。
太鼓はおもに前座さんが受け持っています。前座さんは全ての出囃子の太鼓も覚えなくてはなりません。また笛が吹ける場合は笛も吹くこともあります。
出囃子を演奏する場所はどこ?
出囃子は舞台袖で演奏されます。
客席からは演奏している様子を見ることはできませんが、下座さんは御簾ごしに演奏します。
落語家さんが高座にあがり、客席に向かってお辞儀をするタイミングで出囃子の演奏が終わるように動作を見ながら対応しています。
まとめ
寄席に通っている落語通になると、出囃子を聞いただけで、どの落語家さんなのかわかるらしいです。
まだまだ、そこまでの領域に達していませんが、寄席やホール落語に出かけたときは、落語だけではなく出囃子にも注目してみたいと思います。
それにしても、出囃子を演奏する方になるにはどうしたらいいんだろう。
調べてみます。
では。

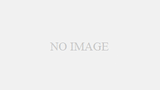

コメント